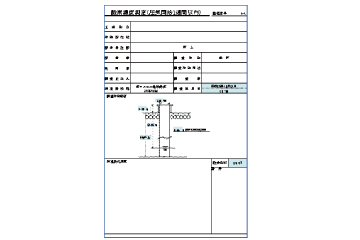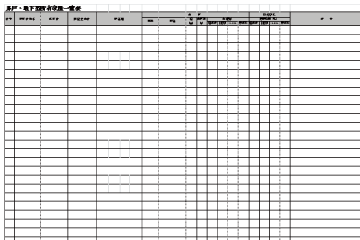大気汚染(空気環境)調査
酸欠調査(酸素欠乏調査)
潜函工法、圧気工法等による掘削作業を行なう場合、酸素欠乏症等防止規則により、周辺区域に漏出する酸素欠乏の空気による酸素欠乏症の発生に必要な処置を講ずる事とされています。
その内、当社では周辺区域の漏出危険箇所の調査を行っています。
主な業務内容
- 圧気工法に伴う酸素欠乏調査(酸欠等防止規則に基づく)


酸欠調査(酸素欠乏調査)に関するお見積り・ご依頼・お問い合わせは(株)中央クリエイトへ
下のボタンからお気軽にどうぞ
基本的な酸欠調査(酸素欠乏調査)の実施方法
1. 酸欠調査(酸素欠乏調査)の前に
1-1. 酸素欠乏の発生のしくみ
地下水のくみ上げなどによって地下水の水位が下がっている砂礫層や鉄分を多く含む砂礫層では、空気に触れると地中にある鉄が酸素によって酸化します。反対に言うと、空気は鉄によって酸素を奪われ酸素欠乏空気になってしまいます。
1950年代半ばから、土木工事では、圧力の高い空気を送り込むことによって、地下水の湧水を防ぎながら掘削作業が実施できる「圧気工法」が用いられ始めました。しかし、1960年代になると酸素欠乏事故が多く発生するようになったため、法の整備が進みました。


1-2. 酸素欠乏による人体への影響
大気は、窒素が78.08%、酸素が20.95%、アルゴンが0.93%、この3つの気体で99.9%を占めています。
酸素濃度が18%未満の空気は酸素欠乏空気と呼ばれ、酸素濃度が16%より低下すると酸素欠乏症の症状が現れます。
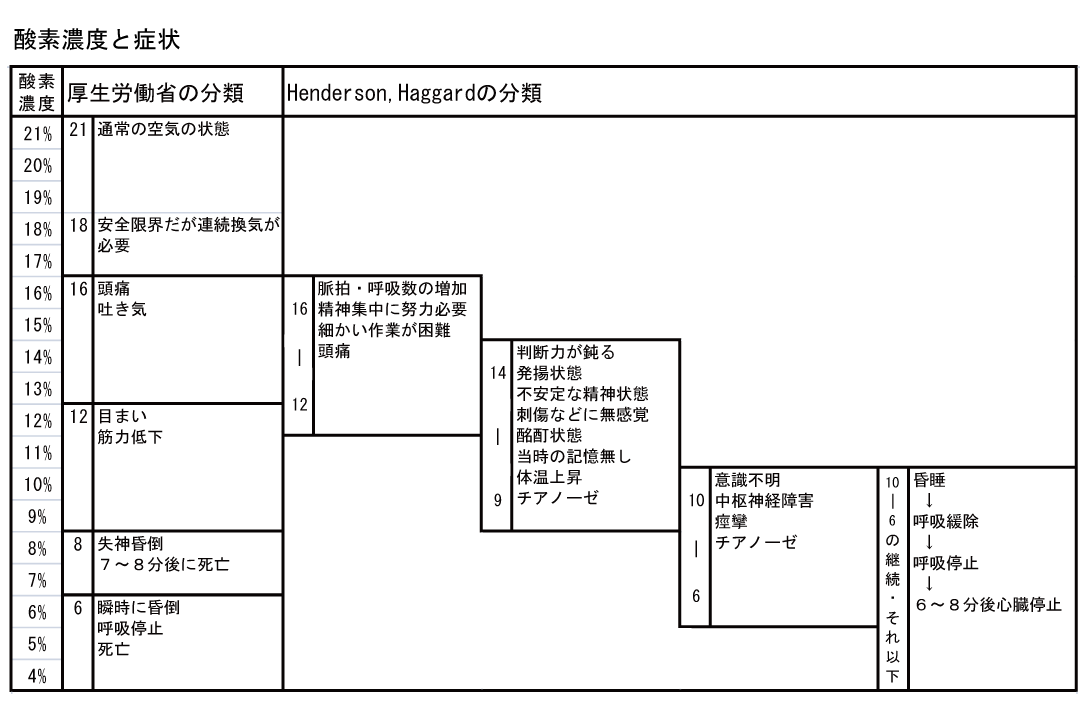
1-3. 酸欠調査の実施の法的根拠
酸欠調査の実施は、酸素欠乏症等防止規則 第三章 特殊な作業における防止措置 第24条(圧気工法に係る措置)において、以下のとおり示されています。
- 「事業者は、令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層が存在する箇所又はこれに隣接する箇所において圧気工法による作業を行うときは、適時、当該作業により酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について、空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調査しなければならない。」
-
令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層とは
「酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他これらに類するものをいう。-略-)の内部。
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
よって簡単に記載すると、圧気工法による作業を行うとき、地層が次の2つのケースの場合は、酸欠調査を実施することになります。
①上層に不透水層があり、含水もしくは湧水がなく又は少ない部分のある砂れき層や隣接する箇所
②上層に不透水層があり、鉄分を含んだ地層が存在する箇所や隣接する箇所
1-4.工事周辺地域における酸素欠乏の発生のしくみ
1)長期間に渡り圧入された空気が、砂礫層を通って井戸などに酸素欠乏空気が噴出するケース
2)過去の工事によって地層内に溜まっていた酸素欠乏空気が、圧入された空気により井戸などに噴出するケース
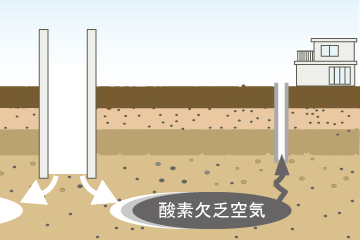
2. 酸欠調査(酸素欠乏調査)の調査方法
2-1. 調査方法
施工箇所より半径1キロの範囲にて、井戸または地下室等の有無調査を行います。
開放井戸や地下室など酸素欠乏の空気が漏出する可能性のある場所に、酸素濃度計のセンサーを挿入し、内部の酸素濃度の測定を行います。

1)井戸
水位測定を行い、開口部付近から水面付近での酸素濃度測定を行います。
2)地下室など
開口部付近及び内部壁面数か所での酸素濃度測定を行います。


2-2. 酸欠調査の測定時期
1)圧気前・事前調査
分布調査を実施し、対象井戸・地下室等を把握し、全件数濃度調査を行います。
2)圧気を始めてから1週間以内
対象井戸・地下室等を全件数もしくは監督員の指示により対象井戸・地下室等をエリアごとに代表箇所を選択し、濃度調査を行います。
3)圧気を始めて1か月後から1週間以内
原則は、圧気を始めてから1週間以内で行った箇所の濃度測定を行います。
4)断気後・事後調査
原則は、圧気を始めてから1週間以内で行った箇所の濃度測定を行います。
2-3. 酸欠調査の測定結果
酸欠調査の結果報告書の参考例は次のとおりです。